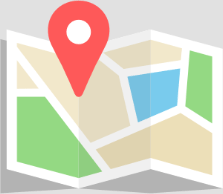本田技研の総会で、小池隆一は攻める。前回で触れた通り、当時の小池は小川企業株式会社の副社長職だった。社長は「最後の大物総会屋」として著名な小川薫。つまり小池は小川薫の部下だったわけだが、まずは小川薫の回想を続けよう。本田技研の総会はその後、以下のような展開となった。
■―――――――――――――――――――― 【写真】アントワープ王立美術館の公式サイトより
■――――――――――――――――――――
<このときの本田技研の総会では、小池君が次々に「動議」を連発する。「本田技研は、子会社で牧場を経営しているが、これは定款違反ではないか」「当社には、何百と関連会社があるが、監査役は三名では足らない。三十名にせよ」「定款によれば、当社の工場所在地の和光市でも株主総会をできるようになっている。しかし、これは株主に不利な条項なので削除を求める」といった調子だった。
あまりに執拗な発言に業を煮やした私は、発言を求めて「一号議案が、まだすんでないので、ボチボチ議事を進めていただきたい」と会社側に助け船を出してもいる。
総会はもめにもめて、休憩をはさんだ。そして小池君は、
「まことに勝手で申しわけないんだけど、自分で動議を出しておいて申しわけないんだけど、この場は、私が出した動議は全部、撤回する。全部、いま撤回させていただきたい」
会社側にすれば、さんざ引っ張っておきながら、それはないだろう、という心境だったろう。まさしく会社に対する徹底的な嫌がらせだった>
当の小川薫が「小池による徹底的な嫌がらせ」と言い残せば、定着するのも無理はない。しかし小池によれば、きちんとした事情がある。その説明を聞けば、小川薫の発言にウソはないにしても、語っていない部分が多いようにも思えてくる。
小川薫自身が記しているが、当時の小川は各企業の社長に面談するのが常だった。ところが本田技研は小川薫を袖にする。頭にきた小川は当時、配下だった小池に相談する。そして小池が総会に登場することになる。
小川薫は小池に攻めさせてマッチポンプを企んだのだ。小川の意を汲んでいたはずの小池だが、この総会の休憩中に三菱銀行から連絡を受ける。
「小池さん、申し訳ないんだが、うちの役員がそっちに行っているんですが、総会が終わらずにまだ帰れないといっているんです。上森顧問に相談させていただいても宜しいでしょうか」
上森顧問とは上森子鉄だ。異名なら小池は「最後の総会屋」で、小川薫は「最後の大物総会屋」となっているが、上森子鉄は「伝説の総会屋」だという。いずれにしても小池の上司たる小川薫でさえ、上森子鉄のことは「先生」と呼ぶ。小池にとっては到底頭の上がらない「上司の師匠」だった。
■三菱グループの「番人」だった上森子鉄
石川県金沢市生まれの上森は昭和の文豪・菊池寛の書生から文藝春秋勤務などを経て、雑誌『キネマ旬報』の発行者としても知られていた。
小池は後に、総会屋で月刊誌『現代の眼』主幹だった木島力也の寵愛を受けるが、この上森からも目をかけられる。
ちなみに小池は新潟県加茂市の出身であり、木島力也も新潟県紫雲寺町(現・新発田市)と同郷だ。石川県生まれの上森を並べれば、3人は日本海の出身となるわけだが、これは偶然とは思えない部分がある。
地方出身者にとって、東京で同じ地元の人間と出遭った時の感覚は独特のものがあるが、「冬の日本海」が骨身に染みた者同士にも似た連帯が生まれる。低く暗い雲を突きあげるように荒れる日本海の波を原風景として持ち、共に望郷の念を抱く。そんな人間の間には、どこか気脈が通じるのだ。
話を戻せば、上森子鉄は三菱銀行だけでなく、当時でも20社を越える上場企業に顧問室を持ち、各社から「源泉徴収された顧問料」を受け取っていた。「企業内総会屋」と形容することができるかもしれない。
普通、こんな総会屋はいない。賛助金や発行する雑誌の広告料で賄うのがいっぱいいっぱいの稼業だ。収入の額と、それを得る方法という意味でも、上森は文字通り雲の上の存在だったのだ。
<日本の代表的企業といわれる大会社には、ほとんどこの人のパイプがつながれており、三菱グループでいえば、その中枢である三菱銀行の株主総会は彼によって握られていると言われる。……とにかく三菱財閥本家である岩崎家でのパーティに出席できる『総会屋』はこの人しかいないといわれる……(『ドキュメント総会屋』小野田修二)>
三菱銀行が、その上森に相談すると言うほど困っているのであれば、小池も黙るしかない。
「わかりました。上森さんに言うことはないですよ。質問は終わりますから。総会は終わらせますよ」
小池は休憩終了後、自身が提案した動議を全て撤回する。そして今の小池は「小川は本田の社長に会えずに悔しいもんだから、私に意趣返しをさせたんですよ」と振り返る。
語る者が2人いて、それぞれの立場によって「真実性」は多分に揺らぐ。とはいえ、それは片方どちらかの真実が間違っていることを意味しない。所詮は2人が見る角度の違いにしか過ぎないのだ。
■「肩書や地位が最後に嘘をつくんです、自分を守るためだけに、嘘をつくんです」
「世紀の贋作作家」ルサールと小池は、ブリュッセルの広場、グラン・プラスのカフェで何時間も語り合った。ヨーロッパで最も美しい広場とも言われ、話題は絵画の審美や、物事の「真偽」にまで弾んだ。
ルサールの部屋に無造作に置かれた〝名画〟の数々が、よほど小池には印象深かったのだろう。日本からわざわざ「贋作の真作」を観たい一心で、神の手を持つ画家と語らうことを望んできたのだから、無理もない。
「本物とは何かということですよね。こうして、本物以上のものが出来上がってしまうわけですから。そうすると、われわれが有難がっている本物というのは本当は何なのかということを考えざるをえなくなりますよね。つまり、肩書きとか、地位とかじゃない、真実の価値は何かということなんですよね。もちろん、一番いいものは、どんなものでも、古今東西、富めるところに流れるというのは同じなのでしょう。でも、それと真実の価値というのは異なるということ。ルサールさんの絵を前にすると、そういうことをまさに胸に突きつけられる思いです。日本人は、肩書きとか地位が好きなんですが、そういうものが最後には嘘をつくんです。それも、自分を守るためだけに、嘘をつくんです」
小池の語る信条を、私が細かく英訳して伝えている間、決して饒舌ではないルサールは、小池の目を見つめながら何度も、何度も深く頷く。そして小池はルサールにこうも告げた。
「正義は決して法のなかにあるのではなくて、それはきっと心のなかにあるんでしょう」
神の手を持つ世紀の贋作画家、ルサールもまた、贋作を描くことで利益を得ようと目論んだわけでもなく、ただ絵を描きたい一心で、偶然に流れ着いた場所で必死になった末、「ルグロ事件」の主人公となってしまっていた。
小池も前半生を必死で生き抜くなかで、はからずも居場所を見つけてしまった。それが世間からは「総会屋」といわれる場所であり、そして82年10月に「違法な場所」「非合法な場所」となってしまう。
無論、社会悪を法が規定し、罰することに「悪意」があろうはずもない。だが法によって「悪」の枠組みが形作られ、定型化されることによって、そこで生きてきた者は「憎まれるべき存在」となってしまう──そんなところを、小池の心は巡っていただろう。小池は自身の前半生を首肯することはない。むしろ努めて批判的でさえある。
小池は表と裏、本物と偽物が表裏一体と化した世界に生きてきた。だからこそ「価値」についての思いは、非常に強かったのかもしれない。自分自身の責任と言えばそれまでだが、流れの中で気がつけば、いきなり「悪」にされてしまう。そんな経験を持つという点で、ルサールと小池の人生は重なっていた。
ルサールにとってもまた、小池の真剣な語らいと信条に共鳴するところがあったのだろう。「自分の友人に小池を紹介したい」と言った。この世で最も心を許し、自身の過去など全てを共有する、最も大切な友人の名前が告げられた。私は小さく驚きながら、納得していた。
小池の言葉は間違いなく、ルサールの心を開いていた。彼が紹介する友人とは、弁護士のヴァン・ダムと、その妻だ。そして私たちはドーヴァー海峡に面したオステンドという海辺の町を訪れた。そこには夫妻の別荘があったのだ。現地では彼らの所有するヨットで食事が振る舞われたのだが、小池は中でもムール貝のスープを特に気に入った。これを日本に持っていけば必ずお客がつくと喜んだ。
ブリュッセルから特急で一時間半ほどのオステンドは、海を渡れば、もうイギリスだった。関東でいえば、逗子や葉山といった都会人の保養地の趣がある。夫妻の部屋には、ルサールが贈った多くの直筆の絵が飾られていた。
モロッコで大きな個展を開き、銀行家などの得意客も抱えているルサールが、今も贋作を生業にしているとは思えなかった。図らずも贋作作家となってしまった過去を強く戒め、逞しく今と将来を見つめている印象を受けた。
その姿は、人目をはばかるようにして子供を育て、妻を思い遣ることのみに喜びを感じて生きている小池の姿と、やはりどこか重なって見えた。
小池は逮捕された後、家族のため真っ当に、後ろ指を指されないよう生きてきた。ルサールも自身の運命を受け入れ、絵を描き続けることで自分と向き合い、修道士のように今を静かに懸命に生きてきた。
■山田慶一こと朴慶鎬によって「身ぐるみ剥がされた」小池隆一
クロワッサンにハムとチーズ、そしてコーヒーが揃ったコンチネンタル風の朝食を終えた直後のことだった。いったん部屋に上がろうと、エレベーターが下りてくるのを待っていたその時、小池は唐突にこう言った。
「シンドラーのリストっていう映画あるでしょ。あれは感動したねー。主人公がこう言う場面があるんですよ。『お金は汚く集めても、キレイに使えばいいじゃないか』ってね」
すでに〝元〟総会屋となって久しい小池が続けた。
「僕らも、商法改正前は違法じゃなかったんだけど、でも世間は決してそうはみない」
ヨーロッパの首都であるブリュッセルには世界中の外交官が集まる。その生活水準はときに、パリさえも凌ぐといわれる。その街の、お世辞にも高級とは呼べない三ツ星ホテルのロビーで、小池は喉のつっかえを吐きだすかのように、そう呟いてみせた。
97年に証券不祥事は発覚、事件化した。もう世間は忘れ去って久しい。だが企業社会の静寂は、小池が沈黙し続けてきたが故に守られているに過ぎなかった。小池は、しばしばこう漏らした。
「野村証券にしても、大和にしても、あっちの調書に出てきたところだけを、あっちがそういうならば、といって、私は認めてきたわけだから。私からは一切、しゃべってませんから」
中小企業金融公庫総裁の水口弘一のことはとりわけ記憶にあるようだった。
水口は従来、大蔵省の天下りポストであった公庫総裁に、民間出身者として異例の抜擢を受けた人物だった。かつて野村証券副社長を務めた水口こそが、証券不祥事に至る野村のやり方を決めた本人であった。
「水口が料亭に呼んで、一番最初にやり方を全部決めたんです。後の人はみんな、この人が決めたのを引き継いでいただけだから。あとに、中小企業金融公庫の総裁になったけれども、私が当時、彼の名前を出して話していたら、そういう地位にはきっといなかったでしょうね。当時、あれだけの事件になったんですからね。もし新聞とかに名前が出ていれば、当然、そこにはいないでしょう。でも、証取法は時効が短いから、当時も逮捕にはなっていないでしょうけれど、みんな、彼の後の人が捕まったわけですから。水口は時効で逃れたけれど、殺人犯が時効ですと言ったって、そんなものでは済まないでしょう。」
そして、小池は一拍置いて、小さく呟いた。
「お前こそ、贋作じゃないか……」
97年5月、小池は第一勧銀や野村證券など金融関連企業から利益供与を受けた商法違反容疑で逮捕される。
懲役9ヵ月の実刑判決を終えて出所した小池は、鹿児島県へと移住する。東京・六本木の事務所はほぼ引き払い、桜島の噴煙を望む空の広い土地を終の棲家とするべく、かねてから自宅も整えていた。
出所以前から妻と子供と共に現地で暮らしており、移住は出所後に決めた話ではなかった。家族の健康のことを誰より留意する小池にとって、東京よりも抜群に空気が澄む鹿児島への移住は自然な流れだったのだろう。人目を避ける隠居という強いられた意味は皆無だったに違いない。
そんな静謐な生活を送る小池の慟哭の声を聞いたのは、2010年4月20日の夜のことだった。
「私はもうだめだな。長くない……もうどうにもならない……」
小池は電話がつながった瞬間、そうつぶやいた。その声は、小池と知り合ってから5年になろうかという時間のなかで、もちろん、一度として耳にしたことのないものだった。
「本当にもうダメだ。これじゃあ、ゴールデンウィークまで持つかどうかも分からない……とにかく家族だけは支えなければいけないけれど、どうにも……」
そう言って、電話の向こうの声は涙声になり、そして小さな声で「申し訳ない。本当に申し訳ない……」そう言って、電話は切れた。
小池がそこまで崩れ落ちることへの心当たりは少なからずあった。小池は紛れもなく、全てを失いつつあった。これまでの連載でも見てきたが、山田慶一こと朴慶鎬によって、ほとんど身ぐるみ剝がされたも同然だった。
この4月20日の電話以降、小池は希望を失ったようになったかと思えば、生活を建て直すためになりふり構わない猛烈さも見せた。小池の気分の浮揚と沈降の落差は次第に大きくなり、周期の幅も狭まっていくように思えた。だが本当に凄まじかったのは、それでも小池が強く自身を戒めて生きていったことだ。
細かなことに目をつぶれば、大きな報酬が入ってくることが明白な場面もあった。だが、れっきとしたビジネスの局面でさえ、違法なことはもちろん、脱法行為にも手を染めないと踏みとどまることは1度や2度ではなかった。
「後ろ指を差されかねないから、私は絶対にしたくない。それをすれば、あの小池が……とまた言われる。そうすれば家族につらい思いをさせる」
それを聞かされる側からすれば「そこまで経済的に困っている状況ならば、その話を決して断ることはできないだろうな」と思うようなものでさえ、小池はためらうことなく断った。
商法も刑法も総会屋を反社会的な存在と定めている。それは抗いようのない「事実」なのだ。しかし小池は総会屋だったが、出所後は少なくとも父親として子供を育て、家庭人として妻を支えてきた。自身の立ち位置はそれしかなく、人生の終末を良き父親として終えようと考えていたことは間違いない。そのために口をはさめば、顔を出せば「あの小池が……」と言われる状況から、ひたすら逃避していた。
90年代後半から鹿児島で〝隠居〟に入ってからの小池は、そうして、かつての東京での知己の前からも、ほぼ完全に姿を消した。そして2010年、小池自身が危機的状況に陥った時、少なからず力になってくれそうな人間とは、ほぼ音信が途絶えていた。間もなく70歳になろうとしていた小池は、孤独な闘いを強いられた。
その後も、上京の折にはお茶をし、電話での四方山話は幾度となく繰り返してきたが、小池には徐々に希望と絶望の勾配が頻繁に訪れるようになる。それでも決して小池は獣道を歩もうとはせず、違法性のない公道を歩もうとしていた。
もし山田慶一と知りあうことがなければ、小池は2016年の今でも静かに余生を送っていたはずだと思いながら、それは違うかもしれないと考え直す。
恐らく小池の人生は、ブリュッセルを訪れている時には既に狂わされ始めていたのではないか。あの時点では小池自身もまだ、激震の予兆にさえ気づいていなかったが。
■小池隆一が産経新聞の取材にだけ応じた意外な理由
小路を楽しむのならば、アントワープは世界最高だと思わせる。
何よりも時折、海風が、歴史を感じさせる石畳の上を吹き抜けていくのがいい。それもまっすぐではなく、時に小路に沿って蛇行して頬をなでていく。そして何よりも、その風が走っていく、曲がった先の風景は想像もつかない、そんな期待感と、心地よい不安に満ちている。
たどり着く先に何があるのか見えない、そんな時間の流れをゆっくりと感じることができる町だ。そんな空気を小池はどう感じるのだろうか――。
07年1月、旅程のすきを縫うように、ブリュッセルから列車に乗って、アントワープの王立博物館へと小池を連れ出した。博物館から駅へと向かう途上、突然の雨に見舞われた。その時の小池の一言が、総会屋人生を脱したあとのひとつの悟りに違いないと思わせた。大粒の雨がまるで季節外れの雹のように顔に叩きつけてきた。そのときだった。
「いいじゃないですか。ふつうのひとは雨にぬれて、ああ、いやな雨だな、濡れちゃったなと思うでしょう。だけど、こう思えばいいんですよ。雨が汚れを落としてくれてるんだなって。そう考えれば、嫌なことも良く思えるんですよ」
旅をきっかけに、小池が上京する時は会って話した。またある時は、かつての友人との思い出話を語る席にも招かれ、私は小さな交流を始めるようになった。そんなときの帰りがけ、小池はそっと囁くことがあった。
「きっといつか取材したら面白いですよ」
かつて、小池が携帯電話で応じた言葉尻をある作家がとらえて、活字にされたことがあった。小池が「ノーコメント」と伝えたにもかかわらず、コメントにしてしまったのだ。それを目にした小池は、実に寂しそうに電話をかけてきた。
「ものを書くひとたちはなんでああなんでしょうね。そんな上っ面だけに生きるひとたちになんかなにも語れませんよ」
意外かもしれないが、小池がメディアに登場したのは、たった1回に過ぎない。逮捕前に鹿児島の自宅を訪れた産経新聞の記者にのみ取材に応じた。それを報じた記事は、小池の〝肉声〟を掲載した唯一の、最初で最後の活字となる。
要するに小池は大のメディア嫌いと言っていいのだが、ではなぜそのときだけ取材に応じたかという理由は、いかにも小池らしい。
「その時の産経新聞の記者さんのとても丁寧で紳士的な態度が印象に残ったんですね。それで、東京に行った折に必ず連絡しますよと言ったら、わかりましたといって帰って行った。その時の雰囲気がとても紳士だったので、上京したときに、きちんと対応してあげなければ申し訳ないなと思って連絡したんです」
総会屋などというヤクザな商売にある者が、わざわざ相手を選ぶのかと思う向きさえあろう。だが間違いなく、小池は「相手を選ぶ」タイプだ。とはいえ小池の選択は、相手の立場と地位によるのではなく、相対する人間に対する真摯さがあるかないかによるのだった。
小池自身は誰に対しても紳士で真摯であり、相手に対しては言葉遣いどころか、それこそ箸の上げ下げまでを同時に、鋭く観察している。それは決して、総会屋であること、あるいはあったことゆえの警戒感からといったものとはまた別のものであったのではないだろうか。
(第6回につづく)